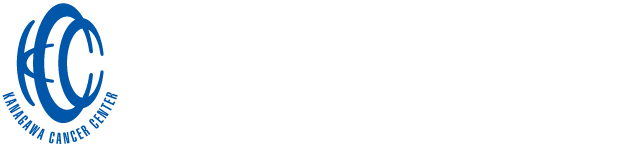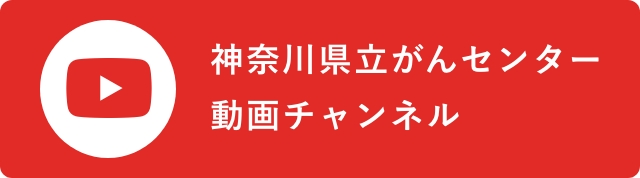患者ご家族のみなさまへ
ページ内のコンテンツ一覧
患者さんの権利と責務
患者さんの権利
- 誰でも平等に良質な医療を受ける権利があります。
- いかなる場合でも、人格を尊重され、尊厳を保障される権利があります。
- 病気や検査・治療について、わかりやすく、十分な説明を受ける権利があります。
- 検査・治療について、自分の意思で選択する権利があります。
- 他の医療機関の医師の意見(セカンド・オピニオン)を求める権利があります。
- 自己の診療情報の開示を求める権利があります。
- 患者さんのプライバシーを尊重し、個人情報が保護される権利があります。
患者さんの責務
- 適切な医療を提供するためには、患者さん御自身の健康に関する情報が必要です。
そのため、これらの情報を医療者にできるだけ正確に伝えてください。 - 患者さん自らが積極的に医療に参加してください。
そのためには、医療者に質問するなどして、医療の内容について十分理解し、納得したうえで、検査や治療方法等を患者さん御自身の意思で選択してください。 - より良い療養環境を維持するため、院内の規律をお守りください。
また、療養上の指示に従うとともに、他の患者さんの治療や病院職員の業務の遂行に支障が生じないよう協力してください。
患者さん・ご家族へのご協力のお願い
患者さんの病気に関する説明と同意について
インフォームド・コンセントとは、十分な説明を受け納得したうえで、患者さん自身に最終的な診療方針を選択していただくことです。当センターでは、インフォームド・コンセントを基本理念の一つとして位置づけています。患者さんの病気の診断や治療に必要な検査や治療法について説明し、患者さんの意思を十分確認したうえで納得いく診療を提供できるよう努めています。
医師の説明がよく理解できない場合には納得できるまでお尋ねください。もし、納得できない場合には、他の病院や他の医師に意見を求める(セカンド・オピニオン)ことをお勧めします。十分に理解・納得をいただきましたら、その処置や治療についての同意書に署名をお願いします。
1. 診療情報の具体的な説明について
ア 医師は、原則として、診療中の患者さんについての、次に掲げる事項等について説明します。
1) 現在の症状及び診断病名
2) 治療の方針
3) 行う予定の治療法について
- 行う予定の検査について、その効果と具体的な方法及び特に注意を要する副作用
- 手術や侵襲的な検査を行う場合には、その概要、危険性、合併症、実施しない場合の病状予測
- 臨床試験や研究などの治療以外の目的も有する場合には、その内容
4) 他の治療法がある場合には、その内容及び利害得失
5) 今後の見通し(予後)
イ 患者さんが未成年あるいは認知症等で判断能力がないと考えられる場合には、診療中の診療情報の提
供については御家族および適切な代理人に対して行います。
2.同意について
病気に関する検査・処置や治療の説明を受け、十分に理解し、納得いただけましたら、同意書に署名をお願いします。
包括同意について
当センターでは、先進的医療を行うとともに、次世代を担う医療人の育成、および医学の進歩を目指して臨床研究、基礎研究を行っております。これらを円滑に進めるため、患者さんへの負担の少ないものなど一定の基準の元に、個別同意の手続きを経ないで実施する『包括同意』での対応を実施しています。
この包括同意に関しては、ご本人からのお申し出により不同意の意思表示が可能です。また、同意・不同意は、お申し出によりいつでも変更できます。
1. 個人情報の利用
当センターでは、「個人情報の保護に関する法律」及び同法に基づく「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に基づき、取得した患者さんの個人情報を含む記録を、所定の目的に利用させていただきます。
当センターでの利用(医療の提供に必要な場合)- 患者さんがお受けになる医療サービス
- 医療保険事務
- 医療保険事務、入退院等病棟管理、会計・経理事務、医療事故等の報告及び医療サービスの向上
- 医療サービスや業務の維持・改善のための基本情報
本人以外への情報提供(患者さんの医療提供のために必要なものです)
- 他の医療機関、薬局、訪問看護ステーション及び介護サービス事業者等との医療サービス等に関しての連携
- 他の医療機関等からの医療サービス等に関しての照会への回答
- 患者さんの診療等に当たり、外部医師等の意見・助言を求める場合
- 検体検査業務その他の業務委託
- 患者さんのご家族等への病状説明
- 医療保険事務の委託、審査支払機関へのレセプト提出、審査支払機関・保険者への照会及び審査支払機関・保険者からの照会への回答
- 関係法令等に基づく行政機関及び司法機関等への提供
- 医師賠償責任保険等に係る医療関連専門団体や保険会社等への相談又は提供
- 国又は地方自治体が実施するがん登録事業への登録
- 他医療機関が行う医学研究等への試料及び情報等の提供(原則匿名化します。関連する法令及び倫理指針に従います。)
- 外部監査機関等への提供
医療、福祉等の向上に資する教育、研究等への利用
- 当センター内で行う学生実習や症例研究
- 学術研究目的で学会や学術誌等において取り扱う匿名化した情報
当センターの個人情報保護方針はこちらからご確認ください。
2. 検査診療行為
以下の検査、診療行為は診療を進める際に普遍的に必要で、患者さんへのご負担が少ないものです。これらの項目については個別の同意を得ずに包括同意を得ているものとして対応させていただきます。一定以上の経験を有する者によって行われますが、時に出血、痺れ、アナフィラキシー、その他予期せぬ合併症を伴うことがあり得ます。このような場合は、合併症の治療は通常の保険診療として行われます。ご理解いただきますようお願いいたします。
- 一般項目:問診、視診、理学的診察、体温・身長・体重・血圧の測定、リハビリテーション、栄養評価、栄養指導、食事の決定
- 検査・モニタリング:血液検査、尿、痰や体液などの検査、心電図等の生理機能検査、 X線撮影、造影剤を用いない CT・MRI 検査、診察室や処置室で行う内視鏡検査(咽頭鏡、喉頭鏡、膀胱鏡等)、心電図、酸素飽和度などのモニター、皮内反応検査。手術等行う場合の梅毒、肝炎、HIVの感染の有無を判定する検査。
- 診療のモニター、画像等
手術室、HCU、放射線治療室、MRI室、CT室、透視室、内視鏡室では、診療上必要な場合、診療の状況をカメラ等により撮影、録音、記録、保管させていただいております。撮影したモニター画像については、 一定期間保管の後に削除しますが、これらの情報を医師等の教育・研究に利用することがあります。
3. 学生等の実習
当センターは、診療を行う医療機関であるとともに、次世代を担う医療人育成を行っております。その一環として、学生等の実習生が診察等に同席させていただくことがあります。患者さんやご家族には、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
4. 診療に伴い発生する情報・資料の利用
当センターでは、診療とともに医学教育や研究を行っており、診療に伴って発生する情報・資料を利用することが必要な場合があります。
【診療に伴い発生する情報・資料】
診療録(カルテ)、X線・CTなどの画像データ、血液検査、病理検査、生理機能検査(心電図、各種超音波検査、聴力検査、平衡機能検査、呼吸機能検査等)など また、血液や尿等の検査試料、診断のために生検した試料、手術で切除した組織等の試料が集められます。 これらの集められた診療情報及び試料は、診療に必要なものとして保管されていますが、その後、診療上不必要となった場合でも、医学研究・教育のために活用させていただきます。
* 上記の診療情報および試料の活用については、生体試料センターから「遺伝子解析を含む生命科学・医学系研究への協力のお願い」として別途説明させていただくことがあります。
5. 包括同意について、ご不明な点がある場合又は意思表示をされる場合
これまで説明してきた包括同意は患者さんの自由意志によるものです。原則として不同意の意思表示がない場合はご同意いただいたものとして対応させていただきますが、ご不明な点がある場合又は不同意の意思表示をされる場合につきましては、がん相談支援センター(病院棟1階中央受付7番窓口)にご相談ください。それぞれの担当部署等をご案内いたします。
カルテ開示
御自身の診療記録の閲覧やコピーを御希望の場合は、担当医師又は総務企画課に開示請求する旨をお申し出ください。(申請書類のお渡し、手続きの説明は総務企画課にて対応いたします)
開示を請求できる方
- 本人
- 法定代理人(患者さん本人が未成年者又は成年被後見人の場合に限る)
- 本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という)
※法定代理人について
患者さん本人が未成年者の場合は、親権者または未成年後見人の方が請求可能です。また、患者さん本人が成年被後見人の場合は、成年後見人の方が請求可能です。
開示までの手順
- はじめに担当医師又は総務企画課にお申し出ください。
- 保有個人情報開示請求書を総務企画課に提出してください。
この際、本人確認のため、官公庁が発行する書類等(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)を提示していただきます。
※請求者が法定代理人の場合は、患者さん本人の親権者又は後見人であることを証明する書類
(戸籍謄本等)が必要です。 - ※請求者が任意代理人の場合は資格を証明する書類(委任状等)が必要です。
- 請求があった日から15日以内に、文書をもって開示、一部開示、不開示の回答をいたします。15日以内に回答が困難な場合は、回答期間を延長させていただく旨を請求者様あてに文書でお知らせいたします。
※当該診療情報に請求者以外の個人情報が含まれている場合で、その方の正当な利益を侵すことになると認められるときや、診断等に関する情報であって、当該診断等に著しい支障が生ずる恐れがあるときなどは、全部または一部を開示しないことがあります。 - 開示または一部開示の決定通知を発送後、来院していただく日程を調整いたします。
本人確認のうえで開示いたしますので、来院時に官公庁が発行する書類等(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)をご持参ください。
※コピーを希望される場合は、所定の料金をお支払いいただきます。 - ※郵送による交付をご希望の場合は、保有個人情報開示請求書の提出時にお申し出ください。
※ 自己またはその他の診療記録の開示についての詳細は、総務企画課までお問い合わせいただくか、
「県立病院における診療情報の提供に関する指針(PDF)」を 御参照ください。
宗教上の理由等により輸血等を拒否する患者さんへの当院の対応方針
当院はがん治療を専門とする医療機関であり、治療の過程において輸血が必要となる場合があります。手術・処置・検査などの医療行為に際し、患者さんが事前に無輸血治療を希望された場合には、その意思を尊重し、可能な限り輸血以外の方法で対応いたします。ただし、患者さんの容態によっては、救命のために輸血が不可避と判断される場合があります。その際には、患者さんによる輸血拒否の意思表示があっても、患者さんの同意を得ずに当院の判断で輸血を実施する「相対的無輸血(※1)」の方針で対応します。これは、患者さんご自身が幼少・高齢・意識障害などにより、輸血の必要性に関する理解・判断・意思表示が困難であり、ご家族が輸血に同意されない場合にも同様です。
治療にあたり輸血が必要と判断された場合でも、なお無輸血を強く希望される患者さんにつきましては、誠に遺憾ながら当院での治療継続は困難となるため、対応可能な医療機関への転院をお勧めしております。当院は「絶対的無輸血(※2)」には賛同しておらず、患者さんやご家族がご用意された「輸血謝絶兼免責証書」等の絶対的無輸血を誓約する免責証明書等に署名・捺印はいたしませんので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
なお、輸血を行う際には、可能な限り事前にご説明いたしますが、救急搬送時や予期せぬ病状の急変など、緊急の場合には事前の十分な説明が困難なことがあります。また、未成年者に対して輸血が救命に必要と判断された場合には、親権者の同意が得られない場合でも輸血を行うことがあります。
医療行為における輸血の必要性は、患者さん一人ひとりの状況により異なります。輸血を行わない場合のリスクや代替療法等については、担当医と十分にご相談ください。
上記の見解は、2008年2月に宗教的輸血拒否に関する合同委員会(日本輸血・細胞治療学会、日本麻酔科学会、日本小児科学会、日本産科婦人科学会、日本外科学会の医療関連5学会および法律・マスコミの代表を含む)が公表した『宗教的輸血拒否に関するガイドライン』に準拠して作成したものです。
今後とも、すべての患者さんに最善の医療を提供すべく努力してまいります。当院の輸血療法に関する考え方につきまして、ご理解いただきますようお願いいたします。
※1【相対的無輸血】
患者の意思を尊重して可能な限り無輸血治療に努力するが、「輸血以外に救命手段がない」事態に至った時には輸血をするという立場・考え方。
※2【絶対的無輸血】
患者の意思を尊重し、たとえいかなる事態になっても輸血をしないという立場・考え方。
かながん情報
神奈川県のがんに関する情報をお伝えします。
神奈川県ホームページ
Free Wi-Fiのご利用について
当センターでは全館でFree Wi-Fiがご利用いただけます。利用に当たっては、利用規約を遵守していただくようお願いいたします。
なお、アクセスが集中した場合、接続が不安定になることがありますので、安定した接続環境が必要な方は、ご自身でポケットWi-Fi等を準備していただくようお願いします。
身体障碍者補助犬の受け入れについて
当センターでは、身体障碍補助犬に則り、身体障碍補助犬の認定を受けた、盲導犬、介助犬の同伴を受け入れています。
- 受け入れ可能な身体障碍補助犬の種類
① 盲導犬:胴に白または黄色のハーネス(胴輪)をしています。
② 聴導犬:目立つ部分に「聴導犬」の表示札が付いています。
③ 介助犬:目立つ部分に「介助犬」の表示札が付いています。 - 補助犬を見かけたら
補助犬は同伴者をサポートするという仕事を担っています。触る、声をかけるなど気を引いたりせず、静かに見守ってください。
同伴者(患者・家族)が補助犬を連れて受診する際の対応はすべて同伴者が行います。(トイレ・検査中の補助犬の待機など)何かお手伝いすることがあるかどうか声をかけ、要望があった場合の対応をお願いします。 - 院内で身体障碍者補助犬が同伴可能な区域
病院棟地下1階〜2階までの外来区域の廊下、トイレ、ラウンジ、外来診察室、待合室、採血室、各検査室の受付、リハビリテーション室、レストラン、コンビニエンスストア、コーヒーショップ、エレベーター - 同伴禁止区域
手術室、 各検査室内、CT室、MRI室、放射線治療位置決め室、HCU、各病棟(3階から7階)
ページガイド
サイトマップを開く