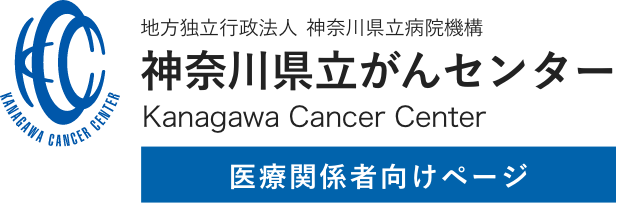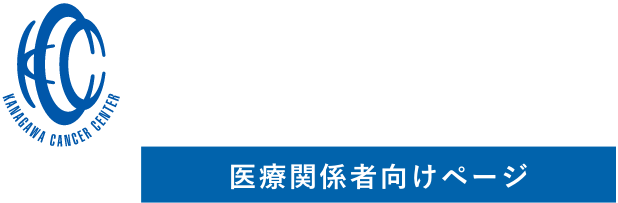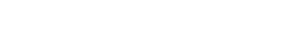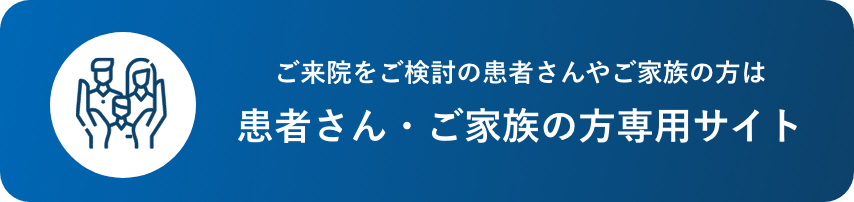呼吸器内科レジデント研修カリキュラム
呼吸器内科レジデント研修カリキュラム
呼吸器悪性腫瘍の診断と治療に携わる専門医の養成
研修目的
呼吸器悪性腫瘍(主として肺がん、他に悪性胸膜中皮腫、胸腺腫など)の診断と治療を中心として、多くの症例を経験し、肺がんなどの診断・治療について幅広い知識を習得し、臨床腫瘍学に関することについて広く身につける。
年度別到達目標
1年目到達目標
診断
- 肺がんの画像診断、病期分類に対する理解と実施
- 気管支鏡の基本的手技
治療
- 病期分類と患者の生理学的機能を考慮した治療法決定
- 化学療法、放射線療法適応の基本的理解
- がん化学療法の計画と実施、合併症対策
- 臨床試験(第Ⅰ相、Ⅱ相、Ⅲ相試験)の理解
- 治験・受託研究の理解
- 小治療手技の実施(胸腔穿刺、胸腔ドレナージ、心嚢ドレナージ、IVH挿入など)
2年目到達目標
診断
- 肺がんの画像診断、病期分類に対する理解と実施
- 気管支鏡の基本的手技
治療
- 病期分類と患者の生理学的機能を考慮した治療法決定
- 化学療法、放射線療法適応の基本的理解
- がん化学療法の計画と実施、合併症対策
- 臨床試験(第Ⅰ相、Ⅱ相、Ⅲ相試験)の理解
- 治験・受託研究の理解
- 小治療手技の実施(胸腔穿刺、胸腔ドレナージ、心嚢ドレナージ、IVH挿入など)
その他
- 患者及び家族とのコミュニケーション
- インフォームドコンセント・医療スタッフとの協調、協力
- 症例検討会への参加
- 文献検索等の情報収集
- 学会活動
- 日本呼吸器学会、日本内科学会、日本放射線学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本肺癌学会、日本臨床腫瘍学会、日本癌治療学会、日本がん検診診断学会、日本肺癌学会関東支部会(3・6・12月)、日本呼吸器内視鏡学会関東支部会等へ演題を提出し発表する。
- 厚生労働省研究班の班会議(JCOG、画像や病理の班会議)への参加および発表
- 論文執筆
学会での発表や基礎研究があれば、その結果等を論文にまとめることが望ましい。
3年目到達目標
上記事項について、さらに理解を深め、疑問点があればそれを解決する努力をする。さらに学会活動や論文作成について積極的に行う。各種専門医取得の要件を満たすこと。
全年次を通して
入院患者6-8名の担当医となり、その胸部X線写真・CT写真の読影、気管支鏡検査の施行、各種検査の指示を適切に行う。Ⅰ・Ⅱ期肺がん患者に対しては手術を主体とした治療の説明を、Ⅲ期肺がん患者に対しては手術・放射線療法・化学療法または放射線療法・化学療法の説明と実施を、切除不能のⅢ・Ⅳ期肺がん患者に対しては放射線療法・化学療法または化学療法を主体とした治療の説明(抗がん剤同意書や治療説明書の作成)と実施を、緩和医療が必要な場合にはその説明と手配を行う。
縦隔腫瘍や悪性胸膜中皮腫などの悪性疾患についても、手術や化学療法について説明し、進行例では化学療法を実施する。抗がん剤の効果と副作用についての知識、臨床試験についての理解、緩和医療についての理解を深める。
指導体制
- 研修指導日本内科学会認定内科医、日本呼吸器学会専門医・指導医、日本呼吸器内視鏡学会専門医・指導医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医・暫定指導医、日本がん治療認定機構がん治療認定医、米国臨床腫瘍学会Active member、感染症管理医師(ICD)、が行う。
- 原則として、主治医として常時6-8名の患者を受け持ち、指導医やスタッフとともにその診療を通して研修目標を達成する。
- 定期的に研修目標達成の進捗具合をチェックする。
- 毎日指導医と連絡をとり、その日の研修内容と結果をチェックする。
- 個々のレジデントの目標達成度を適宜チェックし、その欠点や弱点を補うために適宜受け持ち患者や研修スケジュールを調整する。
研修内容
- 病棟研修
- 入院受け持ち患者の回診および診療:毎日、必要に応じて夜間・休日も
- 診療録の記載:毎日遅滞なく記載する、必要に応じて夜間・休日も
- カンファレンスでの受け持ち患者の症例提示(毎週火曜15:00)とその後の全員回診での患者紹介
- 点滴当番(週1回)
- 呼吸器外科切除例の病理切り出し(毎週金曜14:00)
- 外来研修
- 気管支鏡検査(TBLB、EVUSなど)の実施(毎週火曜日・金曜日午前)
- 胸部CT造影検査、CT透視下の生検とマーキングの実施と読影および読影カンファランス(毎週木曜日午後)
- 患者の診療:必要に応じて再来患者の診察
- 気管支鏡所見の読影と診断
- カンファランス(C)への参加
- 気管支鏡所見の読影C(毎週金曜8:15)
- 内科症例・手術例の治療方針C(チェストC:毎週金曜16:30)
- 切除例病理標本切り出し(毎週金曜14:00)
- 病院CPC(年2-3回)と胸部病理臨床C(年数回)
- 抄読会への参加(毎週金曜8:00)
- 神奈川肺癌研究会への参加(毎月第3木曜19:00)
- 指導医とともに各医師会のカンファランスに参加して、読影法や説明法について学び、また開業医などとの意見交換により、医療現場の実情を理解する(月4-5箇所、19:30、各地医師会)
スケジュール
研修評価方法
部長による研修評価のほか、他スタッフにより逐次評価を受け、目標達成度のチェックを行う。二年次終了または三年次終了時に終了記念講演において発表を行い、自己評価を行う。
![]()
医療関係者の方へMedical personnel